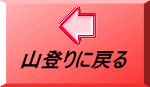

所属している 雷鳥クラブ、軟弱登山クラブ 以外の山行記録です
(個人山行、SNS系の山登り、放浪旅の途中など)
百名山とか人気のある山より、静かな山が好きです

※筑波山とか宝篋山は練習で登るので除きます。
2023.2.8現在
| 67 | ||||
| 66 | ↑ | 1月22日〜 | 笹子雁ヶ腹摺山、七面山 櫛形山 |
コロナ禍で昨年も登れなかった冬の七面山日帰り、前日に足慣らしで笹子雁ヶ腹摺山 (雁ヶ腹摺山シリーズ)、翌日帰る前に近くの南アルプスの前衛・櫛形山に登ってきた |
| 65 | 2023年 | 1月15日 | 小野子三山 | 昨年、軟弱登山クラブで十二ヶ岳だけで敗退したので、冬に高山村側から再挑戦! |
| 64 | 12月12日 | 榛名富士 | 山旅ばっかりの年だったので静養で温泉に。でもロープウェイで行ける山だったので 40数年ぶりに寄ってみた。前回は真冬に母親を連れて行った気がする。 |
|
| 63 | 11月25日〜 | 旭岳、大戸岳 | 旭岳は裏那須の幻の山、私は北アの剣岳似と思うが東洋のマッターホルンという人も 大戸岳は地味な山だと思っていたが、登ると山頂付近は中々の山 |
|
| 62 | 11月7日〜 | 大杉谷、八経ヶ岳 | コロナ禍で行けなかった大杉谷、桃ノ木山荘は空いていて助かったけど、大台ケ原山 への登りはきつかった〜。 奈良奥駆道の厳かな弥山と展望の八経ヶ岳も良かった |
|
| 61 | 11月1日〜 | 大嵐山、流石山、二岐山 | 静かな大嵐山、昔から行きたかった那須の裏側の大峠から登る流石山、今回で3回目 の二岐山 流石山は初夏が良いらしいけど、あの登りは少し暑そうかな? |
|
| 60 | 10月21日〜 | 雨飾山、米山 | 念願の雨飾山は紅葉の真っ盛り、でも人出には閉口、週末の百名山は二度と登らない 米山からの日本海はきれい!もう一度登りたい |
|
| 59 | 10月7日〜 | 石鎚山、剣山、三嶺、 飯野山、恵那山、飯綱山 |
「2022年四国の山旅」週末の石鎚山の混雑には閉口、平日の剣山はのんびり、三嶺は やっぱり四国らしくて良い山、念願の恵那山、飯綱山で北信五岳は完登 |
|
| 58 | 9月11日〜 | 泉ヶ岳、船形山、乳頭山、 五葉山 |
東北地方で去年行きはぐった山、行きにくい山に出かけた。五葉山は行ってみないと わからない良さがある山かな、乳頭山は40数年ぶり。 |
|
| 57 | 7月10日〜 | 北海道駒ヶ岳、雌阿寒岳、 大雪山黒岳、恵山 |
「2022年北海道の山旅」だったけど天候不順なのと、アプローチの林道が荒れていて 登れる山が少なかった。残念 |
|
| 56 | 6月26日〜 | 浅草岳、守門岳、御神楽岳 二ッ箭山 |
ヒメサユリを見に行く、キスゲもたくさん。でもヒルや毒虫もたくさん。目の前で熱中症の 人も、とにかく熱くてハードな山行の連続4日。最終日は1日に2回も雷雨に |
|
| 55 | 5月5日〜 | 湯ノ岳、蓬田岳 箕輪山、鉄山(安達太良) |
常磐道からいつも見える湯ノ岳訪問、芝桜の蓬田岳もついでに登る。 安達太良は登りたかった箕輪山の斜面の残雪で大苦戦、でも湯の平の崖道には感動 |
|
| 54 | 4月24日 | 日和田山 | 地元の山の会の山行が流れたので一人でお出かけ、シャガが満開で感動! | |
| 53 | 3月30日〜 | 伊吹山、賤ケ岳、武奈ヶ岳 御在所岳、鎌ヶ岳 |
滋賀、三重の山旅。 豪雪の伊吹山は残雪で頂上付近の急登に手こずり、武奈ヶ岳は 雪で道探しに大苦戦 御在所岳は人が多いので隣の鎌ヶ岳に登る |
|
| 52 | ↑ | 2月21日〜 | 阿蘇・根子岳、祖母山 韓国岳 |
マイカーで九州へ。阿蘇・根子岳は登っている内に噴火警報レベルが2に、火口付近は 立ち入り禁止 雪の祖母山は風情が有り、韓国岳の雄大さと高千穂峰の美しさは見事 |
| 51 | 2022年 | 1月5日〜 | 雲仙普賢岳、由布岳、 久住山 |
飛行機、レンタカーで九州の冬山に、スタッドレス車が少ないのとタイヤの質が悪く不満。 普賢岳では地元の噴火災害資料館の方に色々と説明していただき感謝 |
| 50 | 11月23日 | 日立アルプス | 日立駅から歩いて助川山→高鈴山→御岩山 たまに行くけど涼しい時が良いかな | |
| 49 | 10月5日 | 安達太良山 | 沼尻スキー場の上の登山口から塩沢登山口までの縦走、くろがね小屋から先が長くて大変! | |
| 48 | 9月21日〜 | 森吉山、太平山・奥岳、 和賀岳、泉岳の下見 |
中々行きにくい北東北の山旅、和賀山はヘビーでした。トラブルも発生したけど | |
| 47 | 9月15日 | 白砂山 | 登山口からの標高差は少ないけれど、アップダウンを繰り返すタフなルートでした | |
| 46 | 8月5日〜 | 斑尾山、信州黒姫山 青海黒姫山、刈羽黒姫山 |
信州五山と、各地の黒姫山を探して登りました。 青海黒姫山の頂上付近は不思議な光景 |
|
| 45 | 7月22日〜 | 雌阿寒岳下見、羅臼岳、 斜里岳、大雪山黒岳下見 十勝岳、富良野岳、アポイ岳 |
北海道の山旅、温泉に入りながら移動して、天気を見ながら山に登っています。 ツアーみたく毎日登るのは無理そうで少なくとも、移動1日+登山1日の2日単位の日程です |
|
| 44 | ↑ | 7月14日〜 | 大博多山、本名御神楽岳 会津朝日岳 |
南会津の奥只見周辺の奥深い山々、本名御神楽は新潟側と会津側が有る新潟側は次回に。 これらの山々では登山者と3日間、ほとんど誰とも会わなかった |
| 43 | 2021年 | 1月14日 | 奥久慈男体山 | SNSつながりで水戸周辺の山友と出かけると、思わぬ人と出会った |
| 42 | 11月6日〜 | 高ジョッキ、浅間隠山、妙義山 | 天気が良さそうなので急遽、上州の山へ出かけた。浅間隠山は倉渕の方から登りたかったが失敗 | |
| 41 | 10月26日〜 | 那須連山縦走 | 峰の茶屋から朝日、三本槍、須立、甲子山、甲子温泉経由、新甲子温泉泊、歩いて戻るが疲れた | |
| 40 | 10月18日〜 | 伯耆大山、宮島弥山 | 中国地方の旅の途中で念願の大山に登る。出来たら冬場に登りたいので下見に(蒜山も)行った | |
| 39 | 10月6日〜 | 霊山、焼石岳、栗駒山 | 紅葉のみちのくへ。台風14号の影響で天候が不順で泉ヶ岳は次回に持ち越し。栗駒山は観光地 | |
| 38 | 9月27日〜 | 編笠山、権現岳、横尾山 | 急遽、南八ヶ岳の編笠山、権現岳、カヤトで有名な横尾山へ行く | |
| 37 | 9月6日〜 | 荒海山、斎藤山、七ヶ岳 | 荒海山は荒天、二日目も荒天なので近くの不思議な斎藤山へ、最終日に晴れて七ヶ岳周遊コース | |
| 36 | 8月19日〜 | 火打山、妙高山、佐武流山 | 火打山は是非とも初夏に再度行きたい。暑くて体力消耗が激しく雨飾山、黒姫山は次回にした | |
| 35 | 8月2日〜 | 坂戸山、荒沢岳、粟ヶ岳 | クサリ天国(地獄?)で有名な荒沢岳と展望の粟ヶ岳、初日には散歩で六日町の坂戸山へ | |
| 34 | 7月2日 | 三浦アルプス、大楠山 | 登ってみたら藪漕ぎだらけで途中で降りてきた。大楠山へ行ったら展望台は立ち入り禁止で散々 | |
| 33 | 6月27日 | 蕎麦粒山 | 念願の蕎麦粒山。林道の開通を待てず、長い仙元尾根をひたすら登るも、頂上は虫ブンブン | |
| 32 | 6月18日 | 三国峠から平標山 | 三国峠→三国山→三角山→太源多山(名前違い)→平標山と縦走、天気良くきれいな草原を歩く | |
| 31 | 6月11日 | 鋸山 | 新型コロナの警戒解除後初(筑波山以外)、浜金谷駅から歴史ある車力道を登る | |
| 30 | 4月11日 | 足尾山、加波山 | つくし湖からキノコ山、足尾山、加波山へ | |
| 29 | 4月8日 | 日立アルプス | 日鉱記念館から御岩山、高鈴山、戻って神峰山、下山路を間違えて藪漕ぎをしてしまった(笑) | |
| 28 | 3月15日 | 鶏足山 | 次々のメンバーで三椏で有名な山(鶏足山、焼森山)に行く。ちょうど満開を楽しめた | |
| 27 | 3月9日 | 金剛山 | 大阪に行ったついでに名物の金剛山へ、何回登ったかを競う山らしい。8,000回の人もいた | |
| 26 | 2月7日 | 明神ヶ岳 | 次々のメンバーで冬景色を見に行ったら暖冬で春の景色だった | |
| 25 | 2月7日 | 日光・庵滝 | 知り合った人と出かけたけど、滝の手前でリタイア。次回、再挑戦かな | |
| 24 | ↑ | 2月1日 | 大楠山 | 下見で出かけ、伊豆半島、富士山、三浦半島、房総半島、大島、東京、横浜が展望できた |
| 23 | 2020年 | 1月20日〜 | 雲取山 | 3人で電車で行く、寒いが冬晴れの良い天気。楽しい雪遊びだった |
| 22 | 12月27日 | 八溝山 | 頂上までクルマで行ける山、時間があれば頂上付近だけでも歩きたかった | |
| 21 | 11月9日 | 大峯山・釈迦ヶ岳 | 世界遺産の大峯山奥駈道(おくがけみち)の一部、長ーい大峯山地 | |
| 20 | 11月6日 | 大台ケ原山・日出ヶ岳 | 日出ヶ岳が最高峰、百名山中で一、二を争う楽な山 晴れたのですごい眺望 | |
| 19 | 10月7日 | 姫神山 | 岩手山の向かいにある特徴的な山、コースタイムの時間ほどかからなかった | |
| 18 | 10月6日 | 岩手山 | 前日に八幡平に行ったがやっぱり頂上は雨風、岩手山は見かけほど急登では無かった | |
| 17 | 8月24日 | 高妻(たかづま)山 | 渡渉失敗、稜線もアップダウンの連続。頂上手前の300mの大岩壁は圧巻、疲れた | |
| 16 | 8月21日 | 鳥甲(とりかぶと)山 | ムジナ平から登るも暑いのとナイフエッジの稜線を何時間も歩き緊張で疲労困憊 | |
| 15 | 8月20日 | 苗場山 | 秘境の秋山郷の三合目から登るも、頂上以後はゲリラ豪雨に会い土砂降りの中を下山 | |
| 14 | 6月25日 | 羊蹄山(蝦夷富士) | 続いてニセコに向かい蝦夷富士に登るも1,500mの高低差は大変 | |
| 13 | 6月23日 | 大雪山旭岳 | 北海道旅行第三弾の前に山登り、念願の大雪山は雄大だった | |
| 12 | ↑ | 4月29日 | 弥彦山 | 弥彦スカイライン駐車場から登った |
| 11 | 2019年 | 1月20日 | 愛宕山、他 | 茨城県の低山、愛宕山、難台山、吾国山のSNS系ハイキング |
| 10 | 6月24日 | 利尻富士 | 隣の利尻島に移動し登るがやはり雨模様、下山中に濡れた岩にすべり大けがをする | |
| 9 | ↑ | 6月22日 | 礼文岳 | 旅の途中で山登り、雨天で視界無しだった |
| 8 | 2018年 | 5月22日 | 八丈富士 | 中腹の牧場近くから登る、風が強く外輪山は周遊出来なかった |
| 7 | 9月3日 | 雄山 | 友人たちと室堂のみくりが池山荘から往復した | |
| 6 | 8月6日 | 月山 | 鳥海山の翌々日に登る、信仰の山なので登る人の数は多く山屋さんだけではないです | |
| 5 | 8月4日 | 鳥海山 | お花畑とガレた新山頂上、数kmの雪渓がいくつも続くのは雄大です。日帰り突貫登山 | |
| 4 | 7月21日 | 身延山 | 富士登山の翌日なのでロープウェイを使って登る、でも本堂への階段は急登! | |
| 3 | ↑ | 7月20日 | 富士山 | 富士宮口からの弾丸登山、お鉢めぐりは出来ず。降り始めたら高山病でひどい頭痛 |
| 2 | 2017年 | 2月26日 | 伊豆大島三原山 | 外輪山を一周し大島砂漠を堪能した。これも放浪旅に記録有り |
| 1 | 2013年 | 10月21日 | 倉手山 | リタイア後初の山登り、飯豊山荘からの往復。山登りは25年ぶりかな?放浪旅にも記述有り |
今の時代、本当にいろんな山道具が有ります。  30年ぶりに山登りを再開して、道具を再び購入しているところです。 昔と変っているもの、進歩したもの、不要なものなどもありますね。 |
| 買ってみて使ってみて、具合が良いものだけを使う様になります。 あまり人に聞いたことは役に立たない場合が多い(人それぞれなのかも) |
| ネットではもっともらしく理屈をつけて初心者の方に説明していますが、 それを見ているとウソっぽいもの(過大広告)が多い気がします。 テレビショッピングと似ているかな。 |
| 30年ぶりに山登りを再開して、昔の山道具より便利になったなあと思うものは少ないです。 中身はあまり変わっていないと思うけど種類だけはものすごく多くなっています。 |
| 非常用の装備は関心のない人もいるようですね。 自分の事だけを考えるのでは無く同行者の事も、考えるべきだと思っています。 山の中で同行者が万が一の場合、一人だけで下山することは出来ませんよね! |
| ザック類 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山靴 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 山旅用に購入した靴乾燥機 革靴モードもある 1時間程度で乾燥する@2,500円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェア類 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小物 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防寒具 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冬用ギア |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食料品、お菓子 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非常用の装備 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手入れ用品 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||