
�V�R�L�O���@�吙�J
|

����53���ő吙�J�Ɍ������r���A�吙�J�o�R�Z���^�[
�ɗ��������R���͋����x�����A�o�R�͂��o����
���̂��ƍׂ��V�吙����n��A�R���Ղ��̓���i�ނ�
�s���~�܂�ɐ����܂�钓�ԏꂪ����
���̉��Ƀg�C���Ɠ��R���͋��̎����̔��@������
|

���͂���ƃo�b�W�����炦��
|
 |

�d�b�Ń^�N�V�[���ĂԂ��Ƃ��ł��邪���Ԃ������� |

�E���̘H����5�䂭�炢��߂���
�t�^�[������� |

���ꂪ�������i�����I�j
�H���p�̃g���b�N�����܂ɗ��� |

�ǂ�Â܂�ɂ���{���O���d���i�H�����j
|
 |

���d���̘e�̒ʘH��ʂ������ɓo�R�������� |

�k�J�͗ΐF |

11:11�@�o�R�� |

����� |

�吙�J���� |

�������Ȃ��}�ȊR�ł͂Ȃ� |

�����痣�ꂸ�A���܂ɂ��ނ��炢�łn�j |

���ꂢ�Ȍk�J�� |

1_������� |

��̘e���A�o������~�肽�肵�Ȃ���i�� |

�L�͌� |

2_�\�J��
|

�\�J�쌴 |

3_�n���J�� |

�g�t |

�������ʌv |
 |
 |
 |
 |

4_���Y���� |
 |

���̋��͌��\����
��l�ŗh�炵�Ȃ����n��� |
 |

���z�J�o�� |
 |
 |

�G�������h�O���[���̑� |
 |

��q�� |

�g��F�썑������ |

������������� |
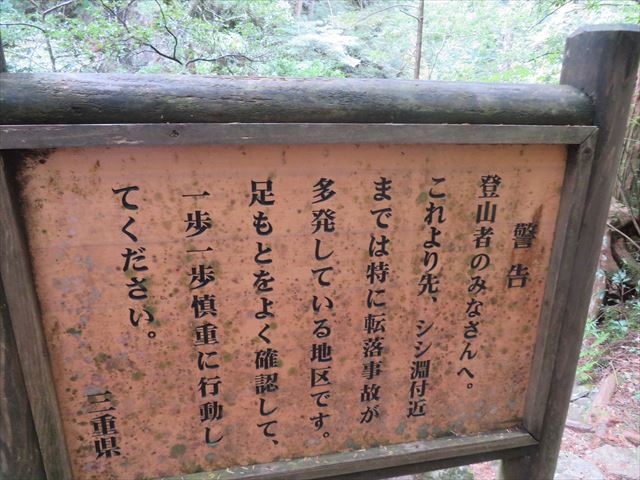 |

���ɃV�V���������Ă��� |

���Z���̃g���l����ʂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ� |
 |


�V�V���̊�̏�łł����ɂ��� |

�����̌�͑��o�� |

���悯�̃Q�[�g�� |

��͂����ƍ����Ƃ��납�痬��o�Ă��� |
 |

��ǂ̘e�́@5_�������� |

���̒������� |

�܂Â��Ƙe���痎������
|
 |

6_��Ώ��� |

���a����ɂ́u�吙�J�o�R���������Z�p�w�j�v
���������̂ɁA���̑厖�̂��N�����̂� |

�s���J�o�� |

��ɓo�鋌���������� |

���ݐՂ����� |
 |

14:40�@�����n�߂�3���Ԕ�
����Ɠ��̖؎R�̉Ƃɓ��� |

7_���̖ؒ� |

�㗬��
|

|

1�K�̍������ʏ��A�E���g�C��
2�������̕��� |

�����̒��� |
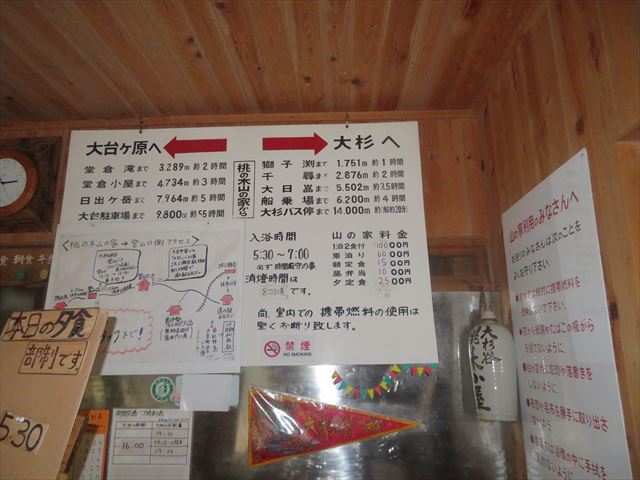 |
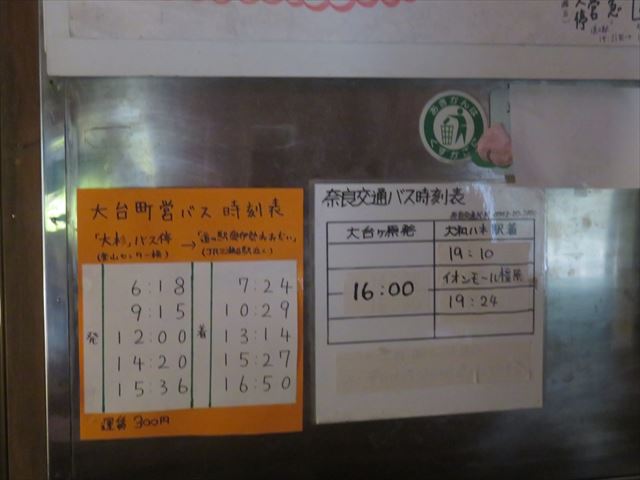 |
 |

�퉷���Ǝv���Ă��������� |

1�K�̒���
���̏�����邪�l�������Ƃ��̂ݎg��
�����͕ʂ̓� |

���߂������^������ |

17:30�@�[�т̓J���[�����ƃg���J�c |

����̉��͈��ݕ���p�p�̐��������� |

19:13�@�݂�ȐQ�n�߂Ă���
�������鎖���������A��������ꏊ���������A
�d�g������Ȃ��̂ŁA�Ƃɂ����Q�Ă���
���т��Ƃ������ɕ��������ȊO�ɐÂ������� |
2022.11.8�@����6���ɋN���Ē��H

5:45�ɓd�C�����ċN����
�����͂�̗ʂ͏��Ȃ߂ɂ��Ă������
|

�H�� |

�H�����O���猩�� |

6:33�@���P���Ɍ����ďo������i1�Ԗځj
|

���ʂ������͖��� |

�P��̒��ӏ��� |
 |

���c����x�e�� |

���c���� |

�R�̓��Ђ��L���̂Ŋ�Ȃ��͂Ȃ�
2�i�ɂȂ��Ă���Ƃ���Ⴂ�����Ղ� |

8_���c����� |
 |

�����P6�N�̍��J�ЊQ�ŕ����n�� |

��̏��K���ɓn�����
�ӊO�Ƀy���L�̃}�[�L���O�����Ȃ� |

���� |
 |

���O�̗R���͕s�� |
 |

9_�B���
|
 |

�^���Y��͗ǂ������Ȃ� |
 |

10_���q�� |
 |
 |

��₱�������ǁ@11_���q���
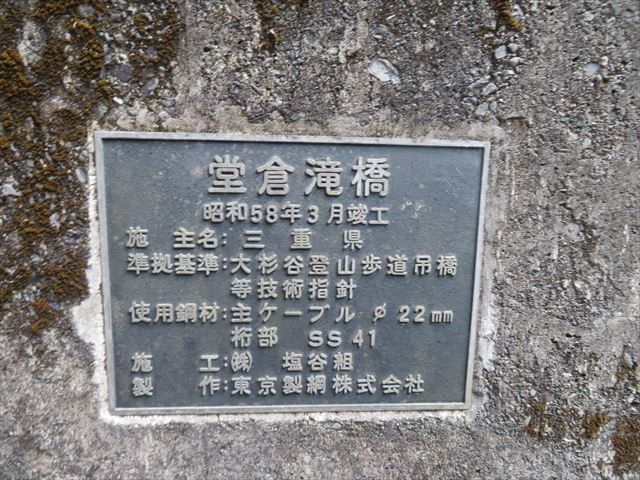 |

���q�� |

�����܂ł͑��ɓo�艺�肪��������
���ꂩ��̓o�肪�������� |

9:40�@�����n�߂Ė�3����
����Ɨѓ��ɏo�� |
 |

�o�������o�R�� |


|

�т̉��Ɉ��J������������ |

�ѓ�����Ăѓo��n�߂�� |

���q����
|
 |

��������͐��т����� |

���o���x�܂ł́A�Ђ�����o�蓹���R���� |

���J�����ւ̕��� |
 |

���o���x���������� |
 |

�V���N�i�Q���ɂ̓V���N�i�Q�����Ȃ�
����������ɂ����������Ă��� |

����傫�Ȃ���o���x |

�V���N�i�Q |

���̂����ɒႢ��������� |

���N�O�Ɍ������i
���o���x�̎R���t�߂��瑱���� |

���ꂪ�R�� |

12:01�@�o��n�߂�5���Ԕ�
�R���ɓ��� |

|

���� |

�ł����������Ċ��� |

�������� |

���h���� |

���������̂ō���Ă�������������ٓ�
|

�����܂��Ɠ��g���A���イ�܂� |

�傫�Ȋp�� |

���P���̒��ԏ�Ɍ����� |
 |

13:12�@���P���ɓ���
�������͏������Ǖ��������Ċ���
�����̏h�͓V�쑺�̃Q�X�g�n�E�X |