
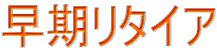 |
|||||||||||||||||||||
     早期リタイアというと皆さん、お金の事ばかり心配します。 そんなのは時間とお金の無駄だと思います。 人生はお金だけではありませんし、死ぬ前に後悔はしたくありません。 定年、70才、仕事 |
|||||||||||||||||||||
| 早期リタイア | 背景 | 長い間仕事生活をしていて、いろいろな事がありました。 最初、仕事に就いた時は、やりたいことを仕事に選んだつもりだったので、一生懸命仕事をしていました。 そのうち何とか仕事を覚え始め、少しづつ自分のやりたい事を仕事の中にこっそり仕込み始めて、少しづつ自分だけの道を歩み始めました。  でもバブルがはじけて、それまでのベースにあった仕事場や一緒に仕事をしていた上司、先輩、後輩、又それまで住んでいるところまでも離れるハメになりました。 |
|||||||||||||||||||
| 経過 | それまで勤めていた都内の事業所は閉鎖され、わずかな人達と郊外の事業所に異動し、それまでの仕事(会社が創業以来やっていた分野)をやめることになり、その残務整理を1人でやる事になりました。 いつまで続くかわからない後ろ向きの仕事を、それまでのお客さんや外注さんに頭を下げながら、毎日続けていました。 そのうちに、世の中に無い新しい製品開発の仕事も並行して行うことになりましたが、これが国内では時期尚早のものらしく、海外ではどうかとアチコチに手を出していたら何とかアメリカ、ドイツ、オーストラリア辺りで火が付き始め、何とか仕事になって来ました。  その新しい仕事に関連して、それまでの専門とは異なる2つの分野に手を付ける様になり、興味を持ち始めました。 会社では相変わらず後ろ向きの仕事が続いていたので、個人的にその新しい分野に取り組み始めました。 |
||||||||||||||||||||
| 転機 | そのうち(嫌々ながらも)仕事の責任だけが大きくなるに反して、会社のバックアップが中々得られずに孤軍奮闘する様になり、過労で入院したりしてストレスが蓄積してきました。  郊外の事業所に転勤してから、日曜日以外はほとんど朝早くから夜遅くまで(土曜も含めて)仕事をせざるを得なかったので、お金を使う暇も有りませんでした。 転勤から10数年経過したある日、今後の生活費とか将来の生活をシミュレーションしてみると、案外今の仕事を続けなくても何とかなりそうな感じが分かりました。 中小企業の普通のサラリーマンでしたが、結婚しても子供もいなかったし、家を持つ前に転勤生活になったのでずっと郊外の社宅扱いのマンションに住み、仕事ばかりしていたせいだと思います。 |
||||||||||||||||||||
| 計画 | そこで考え始めたのは、訳のわからない仕事をこれからも続けるより ・新しい分野の研究 ・これまで忙しくて出来なかったこと ・小さい頃からやりたかった事(学生時代は貧乏だったので) などに手を付けたいと思いました。 それらに手を付けるために、何年かかかりましたが仕事の管理職を外してもらい、ご縁のあった新潟の国立大学の大学院に週末だけ通い始めました。  当初は会社を辞めてから研究生活を始めるつもりだったのですが、うまい具合に勤務しながら通うことになりました。 これが良かったのか悪かったのか、今思うと難しい問題でした。 同時に、これからいろいろな事に手を付けるのに大事なことは 1、金銭的余裕 2、健康 3、気力 の3つだと思ました。 そこで始めたのが 1、生活のシミュレーション、持っている資産の維持管理 2、体力の維持と健康管理 3、やりたい事を続けたり、新しい事にチャレンジする 事でした。 |
||||||||||||||||||||
| 進捗 | このホームページもその進捗やら結果を確認する一部 (全部は公開する訳にはいかないので)です。 同年代の周りの人を見ていると60才で突然定年になり、その時になって初めてどうしようか考え始め、大抵の人はとりあえず継続雇用を選び、数年後に退職される方が多いですね。  継続雇用を選んでみたものの、役職は外されて仕事も今まで通りは出来ず、給与も大幅に減額されて勤労意欲が無くなるようです。 かといって退職しても特にやりたい事も無いし、会社関係の人間関係ももうないし、家に引きこもったりされる方が多い様ですね。 現役時代から諸先輩を見ていたのですが、大体男性は70才頃から急にパワーダウンされて、社会からフェードアウトされる方が多かったですね。 それが早期リタイアを決意するする大きな要因でした。  60才、あるいは65才でリタイアして新しいことをしようと思っても、それ程長い時間は無いと思います。 |
||||||||||||||||||||
| 健康 | 健康のページを参照 マラソン、水泳のページを参照 |
||||||||||||||||||||
| やりたい事 チャレンジ項目 |
ホームページの各欄参照(一部は進捗中) |
||||||||||||||||||||
| 資産の維持、管理 | 生活シミュレーション |
まずは現在の生活の収支をエクセルで集計しました。 そしてリタイア後の生活はどうなるかのシミュレーション、これが難しいかったですね。 実際はどうなるかは分かりませんが希望的な生活を考えました。  支出: 自由な時間があるとして、海外の放浪、これを早期に実行しようと思いました(当時は) 1か所に2ヶ月、これを年2回、5年位続けて目的地を決めて移住しようと思いました。 それに必要な資金を準備して計算しました。 収入: 食うための仕事はもうこりごりだったので収入は当面ゼロ(年金が支給されるまで) 退職時の厚生年金基金の退職積立金と会社関連の退職金が唯一の収入です。 これらと将来もらえそうな年金額を計算しました。 私の生年月日だともらえる年金は 62才から ・特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分 65才からは ・老齢厚生年金が65才から(1と同額) ・老齢基礎年金(国民年金) ・加給年金(妻が65才になるまで) です。 イメージは下図をご覧ください(私は妻の生計を維持していませんが年齢差が有る場合と考える)  具体的にもらえる厚生年金(国民年金を含む)は
私の場合は妻と年齢が5才差ですから70才からは 16万5668円/月になりますが その代わり妻は振替加算の金額1万5402円/年がもらえます。 (妻の厚生年金の金額は知りませんが) 私の場合、その他の収入は早期リタイア後の国民年金基金と個人年金などです。 シミュレーション(Simulation): これは実際の年齢、特に寿命(平均寿命)も入れての計算です。 死んだ後の後片付けは、若い頃に払い込んだ死亡時保険(実は変額保険の解約できなくなったもの)で充当しようと思うので資産を残す必要はありませんが、寿命が延びた時の考慮も必要でした。 但し、もうその頃はお金が有っても使い道は無いと思うので、少額しか考えませんでした。 それらを退職年齢ごとにエクセルで計算しグラフを描きました。  それによると50代前半まで勤めれば充分らしいので、リタイアを52才頃として行動を開始しました。 でも実際はいろいろな事が有り、そうもいかず結局56才のリタイイアでした。 リタイア前の40才代後半から毎年「やりたい事リスト」を年一回作っては更新しています。 最近はこのHPがその代わりなのであまり更新してはいませんが。 |
|||||||||||||||||||
| 資産管理 | 毎年、持っている資産残額の推移を集計、計算してグラフ化しています。  最近は少しですが特別支給の老齢年金が支給されるようになって、収入が有るようになりましたが、それまでは退職金類の食いつぶしで、精神的には良くなかったのですが、呑気に暮らしていました。 本当は以前前作った生活シミュレーションデータとの比較をすれば良いのでしょうが、多分そう大きくは違わない(だろうと思っている)と思い見直してはいません。 |
||||||||||||||||||||
| 資産運用 | リタイアされた方、特に早期リタイアされた方は大抵アルバイトや副業程度の仕事をされて収入を得ているようですね。 私の場合、もう仕事は充分したし、好きでもないことはしたくないし、言いたいことは言いうので、仕事はしません。 そうなると収入は既にもっているもの(資産)と年金類だけになります。 大した資産や年金ではないので、多少はそれらを運用出来たらと思っています。 (それはシミュレーションの範囲外) 資産運用の種類としては、一般的に
リスクのイメージ  などがありますが個人的には 1の国内の銀行預金の金利は現在極めて0に近い値なのでパス 2の不動産はそこそこだと思うのですが手がかかり面倒そうなのでこれも難しいかな 3はいろいろな投資先が有りますが、株や債券は手軽ですが問題もいろいろあります。 債券類は低金利時代なので機関投資家向きかな、でもギリシャショックの時などは大きく変動したり していたのは意外だった 投資信託もやってみた事も有るけど、手数料が高かったり、リアルタイム性に欠けていたり するのが欠点かな 株式も短期だと難しいけど、今は時間があるのでゆっくり考えるのなら可能(寿命は短いけど) 投資信託的な運用で手数料が低く、リアルタイム性の有るETFも現在はある。 4は時間的に無理かな、変動が激しいので張り付く必要があって。 他にやる事が無くてFXに株にハマっているシニアの方もいるみたいだけど。 |
||||||||||||||||||||
株式や債券、投資信託の運用について シニア向けの運用の場合に良く話に出るのは投資信託かも知れません。 投資信託は運用を信託会社に任せるので、知識や経験が無い場合でも安心できるのかな。 ただ、バブルがはじける前だったら株式ベースの投資信託はかなり美味しいものでしたが、今はそうでもありません。 代わりに今は投資信託の運用先として国内/海外のあらゆる分野のものがありますね。 株式の日経平均もバブル崩壊後は下降と迷走を繰りけていましたが、この5年間は上昇気運にある ような感じですが、誰も先の事はわかりません。  うーん、二度と38,900円なんて値にはにはなりそうも無いですが、この先どうなるかは全くの不透明です。 |
|||||||||||||||||||||
ここでバブル後の日本と米国市場を比較して見ます。 日経平均と米国ダウ工業平均との比較(1985年〜2016年)  バブル前の1985年1月と2015年末の値を比較すると 日本は約1.5倍、バブル後の値は迷走しています(ここ5年は少し上昇機運かも) 米国は傾向として右肩上がりで、なんと約8倍にもなっています。 米国のみならず世界中を巻き込んだ2008年9月のリーマンショク時の値を比較してみます。  米国はショックの急落後もすぐに回復を始めていて数年で元の値に戻っています。 日経平均とドル円の推移(1985年〜2016年)  バブル崩壊(1989年)後のドル円値は、ゆるやかに円高傾向の様です。 |
|||||||||||||||||||||
| それからすると投資先は米国の株式あたりが良さそうですが、懸案事項は為替ですかね。 ドル/円の為替はここ10年くらいは80〜120円/ドルで推移してきましたが、今後は不明です。  |
|||||||||||||||||||||
いざ定年になってから資産の運用とか言われても、それまでに経験の無い方にとっては何をして良いかわからないし、怖いものだと思います。  銀行の預金でしたら絶対に元本は保証されているので安心だけど、現在は何十年お金を預けてもほとんど増えません。 かといって元本保証で利息の良いものなんて今は絶対にありません。 自分の責任で自分の将来を選択しないといけない時代だと思います。 |
|||||||||||||||||||||